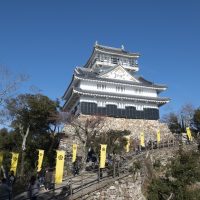2020年に発生したCOVID-19パンデミックは、交通事業者に多大な打撃を与えた。新型コロナが5類感染症に指定されて社会が日常を取り戻しつつある現在(2023.5)でも、交通事業者の経営環境は厳しい。影響を強く受けているのは通勤定期の減少と高齢者の出控え及びインバウンドの減少だ。激変したマーケットは、コロナ前の状況に完全には戻らないと前提を置く場合、名古屋市交通局の次なる経営改革のテーマはどこに置くべきだろうか。
1.交通マーケットの状況 -DXは進化を続け、通勤定期は戻らない-
コロナ禍が産み落としたリモートスタイルは、通勤行動を減少させた。この傾向は首都圏で顕著で、コロナ禍前に比して2~3割の通勤客の減少が見られる(vol.103ご参照)。名古屋圏と関西圏はもう少し戻っているが、それでも通勤客は減少しており、交通事業者にとっては定期券収入の減少へと繋がっている。
また、高齢者への感染リスクの啓発が普及した結果、高齢者の出控えが定着し、定期外利用(一回乗車券購入による利用)や高齢者パス(名古屋市では「敬老パス」)の利用が減少している。外国人観光客によるインバウンド需要もコロナ禍によって消し飛んだ。
但し、高齢者の出控えは、感染症の沈静化とともに元に戻る可能性があり、インバウンドは既に戻りつつあるから、これらの交通需要は徐々に復元する可能性が高い。問題は、通勤定期の需要が元に戻らない可能性だ。リモートスタイルがサービス業のオフィスワークを中心に定着化していることに加えて、今後もDXは進化を続けていくに違いなく、これに伴い通勤離れは今後も継続、或いは漸増していく可能性も高いと見るべきではなかろうか。
そうなれば、通勤定期需要の減少分は完全には戻りきらないという前提で経営を改革していく必要がある。もとより、少子化による学生数の減少で通学定期は減少傾向下にあったから、マーケットの縮小を前提とした経営の持続可能性を追求していく姿勢を持たねばならない。
2.大胆な改革視点をどこに置くべきか -民間交通事業者との連携を深めるべきでは-
筆者は、名古屋市交通事業経営有識者懇談会のメンバーとして議論に参画するにあたり、大胆な経営改革視点をどこに置くべきか自問自答している。名古屋市交通局は、経営健全化計画以来の累次にわたる経営計画の策定と断行により、経営を改善してきた実績がある。この間の真摯な議論とたゆまぬ努力を垣間見てきた身としては、改革成果に敬意を表するところから議論したいと考えている。但し、マーケットが構造的に縮小すると前提を置く場合には、コスト効率を一層に高めることを優先的に取り組む必要があるとも考えている。
その際、可能性を追求したい事は、民間事業者との連携だ。民間の交通事業者は、名古屋市交通局よりもコスト効率が高い(運行コストが安い)という実態があるから、オペレーション(地下鉄とバスの運行)を民間交通事業者に大胆に委ねる方策を考えることが有効だろう。例えば、市営地下鉄鶴舞線は名古屋鉄道と相互直通しているが、鶴舞線の運行の全てを名古屋鉄道に委託すれば、名古屋鉄道のコストで運行が可能になるから直営する費用よりも委託費の方が安くなり、コスト効率を上げることができる。また、相直区間の起終点である上小田井と赤池で運転手の交代が必要となっているが、その必要性もなくなり、ダイヤの余裕も生まれてサービスレベル(評定速度や運行頻度)の向上につながる可能性も出てこよう。唯一の相直運行路線であるからこそ、地下鉄鶴舞線の駅務を含めた全線運行委託は必須の検討課題ではなかろうか。
市営バスについては、これまでに車庫単位で民間委託が実施されているが、これもより大胆な委託を検討することが課題だ。例えば、栄のバスターミナルであるオアシスには、市営バス以外にも名鉄バスや三重交通バスが発着している。オアシスに発着するバス路線の全てを民間交通事業者に委託すれば、ここでもコスト効率は上がるとともに、発着便の諸調整も円滑化するのではなかろうか。
但し、問題もある。それは委託後の名古屋市交通局職員の配置だ。民間委託を大胆に行うほど職員配置について新たな対応が必要だ。しかし、マーケットの構造的変化に対応していく必要が生じた以上、計画的に人員配置をコントロールしながら民間委託という連携を深めることで名古屋市交通局の全体の運行コストを引き下げていく努力が必要な局面に直面していると考えねばならないと思うのだ。
3.まちづくりと社会への貢献も視野に -保有資産の有効活用を-
コスト効率を高めながらマーケットの変化に対応した持続的経営を行うことが求められると同時に、まちづくりと市民社会への貢献についても深度化を検討する必要がある。この観点から筆者の考える2つの課題を述べたい。
第一は、名古屋市内各所にあるバスターミナルの上部空間の利活用だ。市営バスのターミナルは地下鉄との結節点であり、市民生活における交通の要衝だ。しかし、その上部空間は未利用となっている。乗り換え拠点であるから、ここに保育園、クリニック、塾などをはじめ、ドラッグストアや日用雑貨・食材店および飲食店舗などが入居すれば市民は利便性を感じるに違いない。
様々な困難が立ちふさがっていることも理解できる。例えば、地下鉄上部空間であるために構造物の建設が複雑となることや、建設中のバスターミナルの運行を確保するための代替空間の確保や必要経費などがあるだろう。しかし、上部空間の利活用がなされた後の「駅そば」地域の利便性の向上を考えれば、公営企業である名古屋市交通局だけの単独事業として捉えるのではなく、他局と連携してコスト負担をシェアするなどの工夫を凝らす価値は十分にあるはずだ。民間とのコストシェアも事業スキーム次第だ。星ヶ丘や新瑞橋など、上部空間の利活用が有効に思えるバスターミナルはいくつかあるので、これを検討する姿勢を持って頂きたい。
第二は、名古屋市交通局の交通系ICカード「manaca(マナカ)」のモバイル化だ。マナカは着実に普及し、オートチャージを導入するなど進化も遂げてきているが、さらなる進化としてモバイルマナカへの移行を望みたい。モバイル化することによる利便性の向上は、モバイルsuica(スイカ)の利用者であれば異論のないところだと思うが、これを阻む最大の課題はシステムコストが大きい事だという。しかし、マナカは名古屋市交通局と名古屋鉄道が運用しているため、両者が協働してモバイル化することでシステムコストをシェアできる可能性について検討すべき余地があると思う。つまり、マナカを運用する会社を共同出資して設立し、一体的にモバイル化への移行を進め、その開発コストを両者が負担し合うことで単独移行よりもコスト縮減を図ることができるはずだ。
モバイルマナカへの移行による運輸収入の向上は期待できないかもしれないが、suicaに加えてicoca(イコカ=JR西日本の交通系ICカード)もモバイル化しており、将来的にはtoica(トイカ=JR東海の交通系ICカード)もモバイル化を進める可能性もあるため、マナカだけが埋没することを筆者は危惧する。名古屋市のブランド性を高める意味においても、単純な費用対効果で二の足を踏むことなく、検討を進めて頂きたいと思うところだ。
バスターミナルの上部空間とマナカは、名古屋市交通局が有する事業資産であり、これらを一層に有効活用することは、名古屋市を住みよい都市に押し上げ、市民の利便性を高めるインフラとして貢献することになるから、名古屋市交通局の経営使命と言えるはずだ。但し、公営企業体である交通局が単独で進めることを前提とすれば、コスト負担をはじめとして幾重もの障壁があろうから、民間交通事業者や庁内他局との連携を深めることを前提に打開策を探るべきだろう。
「市民の足は市交が守る」という姿勢で開局100周年を迎えた名古屋市交通局は、コロナ禍を契機としたマーケットの構造的な変化に直面した今、大胆な連携方策の導入を視野に入れた経営改革に取り組むべき局面にあると思うのだ。