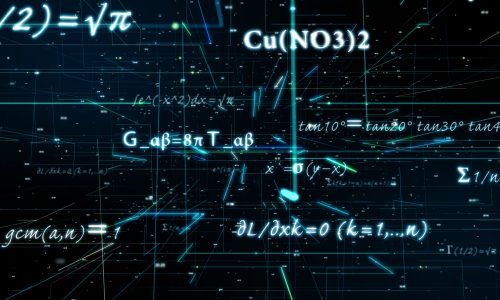(vol.33「その1」からの続きです)
伊勢湾口道路の調査研究において、経済調査班として加わった筆者は、太平洋新国土軸の形成が国土の均衡ある発展に向けて必要だと得心していた。時代が大きく変わった今、今後の国土のあり方をどのように展望すべきか。不明瞭ながらも考えてみたい。
3.事業手法案の構築にも難題山積 -立ちはだかる巨額の建設費用-
経済調査班では、効果の計測と並行して事業手法の検討も進められた。ここに立ちはだかったのは巨額の建設費用である。当時の技術調査班の検討結果からは、橋梁を含む全長約90kmの道路建設費用は約1兆円と積算されていた。これだけの巨費をどのようにして賄うのか?平常時の伊勢湾口道路の推計交通量の料金収入だけではとても賄いきれないし、全額を国費として予算付けることも不可能な情勢だった。担当した筆者は、コスト負担を官民に分散した上で、官が負担する費用を平準化させる工夫が必要だと考えた。民活が必須の情勢だった。
検討に当たっては、国・地方・利用者などでコストを分担する受益者負担のあり方を整理したり、インフラ分野における民間手法の導入事例などを調査した。とりわけ、事例調査を丹念にする必要があったが、国内には運送法上の道路の民活事例はあったものの、道路法上の道路の民活事例はないので、海外諸国に見られる海峡道路等の民活手法を調査した。シドニー・ハーバートンネル(豪)や香港東部海底トンネル、北欧諸国の島嶼部をつなぐ大規模架橋プロジェクトをはじめ、鉄道ではあるがドーバー海峡トンネルなど、様々な事例からエッセンスを学び取って日本流にアレンジする検討に明け暮れた。しかし、当時の制度下ではどれも単純に適用できる状況には無かった。1999年(H11年)にPFI法が制定されて現代的な民活の時代に突入したが、道路整備に導入できるまで機は熟していなかったのである。道路法では民間による整備を認めていなかったし、日本の高速道路は日本道路公団が一手に引き受けていたから、有料道路の経営ノウハウが民間には蓄積されていなかった。また、巨大な道路資産を民間が保有する事は、日本の税制との折り合いが悪く非現実的だった。
そこで、下部工は直轄工事とし、上部工をPFI方式のBTO(Build Transfer Operate)とするスキームなどを想定した。国内でも事例が存在した上下分離方式の変形で、こうすれば直轄負担は減るし、BTOによって官が負担する上部工費用の平準化も図れた。また、あくまでも道路資産の保有は官とした。あとは、料金収入で維持管理費用(修繕費を含む)を民間が賄えるかどうかだが、推計交通量が少なかったので、イギリスの高速道路で導入されていたシャドートールを参考に、日本版シャドートールの導入も考えた。利用者負担による料金収入に加えて、交通量に応じて道路管理者(官)が補填することを考えたのだった。
その他にも、様々なスキームを考えた。いずれにしても制度改正なくしては実現しない民活手法を検討するのだから、大胆な発想に立つことも必要だと考えながら、相対的に実現性が高いと思われるスキームを模索した。膨大なケースのキャッシュフローの試算を重ねながら比較考量してスキームのビルド&スクラップを繰り返した。そして、制度上の問題は残っていたが、概ねの方向性が見え、今後の詳細検討に値するスキームを絞り込んでいた頃、この調査は終焉を迎えた。
調査を実施していた東海幹線道路調査事務所が2009年(H21年)3月をもって閉鎖されたのである。理由は、道路特定財源の一般財源化にあった。揮発油税の使途を道路整備に限定していた従来の道路法が改正され、一般財源として多用途に使うことが出来るようになったのだが、つまりこれは、夢の長大橋の建設財源は確保できない事を意味し、関連する調査は全て打ち切られることになったのである。
4.海峡横断道路は必要だったのか? -「国土の均衡ある発展」の次の考え方は?-
時は2021年となり、伊勢湾口道路の調査に加わった頃からおよそ四半世紀が過ぎた。この間に、時代は大きく変わった。我々は大規模災害を幾度も経験し、インフラの多重化の重要性を強く認識した。東名・名神高速道路は新東名・新名神によって二重化され、リニア中央新幹線によって東海道新幹線も二重化されようとしている。その結果、日本の国土のリダンダンシーは確実に上がりつつある。「国土強靭化」に重点がシフトしたのである。この点では、リダンダンシーに着目した当時の議論は正しかったと言って良い(vol.33「その1」参照)。
一方、人口は全国的に減少に転じ、「国土の均衡ある発展」と言うフレーズは聞かれなくなった。確かに均衡を図るというのはあまりに非現実的だと今になって思う。代わりに「地方創生」が謳われているが、これは人口減少を前提とした地域づくりである。日本の経済エンジンは大都市圏に任せ、地方では人口減少を受け止めながら何とか活力維持を考えようという国是に映る。頼みの綱は交流人口と関係人口だ。地方における地域経営は、観光消費を大都市から誘導し、地域づくりの担い手としては関係人口を含めた支え合いを模索することで生き残りをかけるというトレンドが支配的となりつつあった。
そこに、未曽有のパンデミックが突如発生し、コロナ禍となった。すると大都市圏から脱出して地方に居住し、大都市に所在する企業の仕事をする価値観が芽生え始め、地方はそのライフスタイルを実現する舞台として移住者の確保に力を入れるようになった。地方の人口減少に歯止めをかける希望が再び芽生え始めたのである。
こうした目まぐるしい時代潮流の変遷を踏まえ、太平洋新国土軸の形成に夢を追った筆者は、今後をどう展望すべきか自問自答している。DX時代となれば、大都市圏から離れた地方でも「遠隔」で仕事をし、医療サービスを受け、学習することが可能となる。そうすると広域移動を支える高速交通インフラは不要となるのだろうか。筆者にはそうは思えない。大都市圏からの移住先は、どんな辺境地でも良いとはなるまい。いざという時に大都市にアクセスしやすい事が有利であるに決まっていよう。仕事でも医療でも教育でも、いざという時にはリアルな空間で対面による活動が求められるに違いない。
DX時代に勝ち組となる地方の条件とは、豊かな自然、ゆとりある生活環境、心が通う支え合いが享受できる地域であって、かつ、大都市にアクセスしやすい高速インフラを具備している地域ではなかろうか。経済エンジンは引き続き大都市圏が担い、これを支える人材が地方に分散している国土を思い描く。取引量を増やす(GDPに直結する)活動は大都市圏で行い、取引に必要な情報の整備や事務及び研究・生産活動等を地方圏で行えば、大都市には業務機能集積が残るし、地方には定住人口が増える。そんな相互依存型の国土を目指すべきではないかと筆者は考えている。2030年代は、こうした大都市圏と地方圏の新しい役割分担を前提とした国土の発展を目指すべきではなかろうかと。そうした国土には、広域移動を支える高速交通網をリダンダンシーに配慮しながら整備して行くことが一定に必要だと思う。
仮に、この新しい役割分担を実現する国土の発展を目指すとなった際には、伊勢湾口道路の灯が再びともる事もあるやもしれない。しかし今はまだ、そこまでは五里霧中だ。