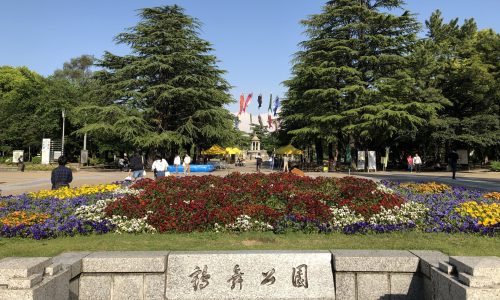現在の名古屋市基本構想は、昭和52年(1977年)に策定された。半世紀近くが経過した今も、名古屋市行政計画の最上位に位置づけられており、大きな祖語を来たしていない事に尊敬の念を表したい。但し、基本構想は普遍性の高い行政方針ではあるべきだが、時代の変化や国の政策を反映する事も重要だ。例えば、今日的にはDX時代が前提に置かれるべき他、リニア開業を念頭に置く必要もある。市長も変わり、そろそろ基本構想改定の時期が到来していると考えたい。そこに求めたいのは国土観と経営的発想だ。
1.名古屋市に迫る趨勢的将来 -衰退前夜の今を直視する姿勢が必要-
2024年の名古屋市人口は233万人で、ここ数年横ばいで推移している。国内総人口の減少が進む中で約230万人を維持しているのは、日本三大都市の一角を誇る名古屋の面目躍如といったところだ。
しかし、安堵ばかりもしていられない。人口増減を自然増減と社会増減に分解すると、いくつもの問題が見えてくる。まず、自然減が加速的に拡大していることだ。2024年では▲11,260人となった。いわゆる少子高齢化の表れであるが、これは人々の価値観に基づく現象であるから、簡単にはトレンドを変える事は出来ない。従って、少子高齢化による自然減は、暫く拡大が続くと見ておかねばならないだろう。
一方、社会増減は15,841人の増加となったため、自然減を補って4,581人の微増となったのであるが、ここにも大きな問題が潜んでいる。約1.6万人の社会増のうち、最も多かったのは海外からの転入超過(約1.4万人)で、国内からの転入超過は約2千人に過ぎない。つまり、名古屋市の社会増の太宗は外国人の増加によって支えられているのである。また、国内からの転入超過の内訳は、20歳代の若者を中心に中部圏から約8千人の転入超過がある一方で、首都圏に対して約▲6千人が転出超過している。首都圏への人口流出は20~30歳代の若者が中心で(約▲4千人)であるから、名古屋市は近県から若者を吸引していると同時に首都圏に若者を送り出していて、人口のダム機能を果たしていない。
更に、0~14歳に目を向けると約2千人の流出超過となっている。中学生までの年齢層であるから自分の意思で転出しているのではなく、親の転出に伴う減少だ。つまり、名古屋市は子育て層の流出という問題も抱えているのだ。子育て層の流出先は名古屋市に隣接する市町が多く(あま市、大治町、北名古屋市など)、子供の成長に伴い暮らしやすい住宅を求める層が、価格高騰する名古屋市内の新築マンションを諦めて転出していると考えられる。
名古屋市への転入者の中核となっている中部圏では、その全域が人口減少であるから、今後はこの転入ボリュームは細ると見るべきだし、首都圏への若者流出に歯止めがかかる傾向は見られず、市内のマンション価格が下落する事は考えられない。従って、名古屋市の抱える2つの人口問題(若者の東京流出と、子育て層の近隣流出)は構造化し、名古屋市の社会増は今後縮小すると見るのが自然だろう。
少子高齢化が進展(自然減)するとともに若者や子育て層が流出(社会減)すると、名古屋市内における消費が萎むという副作用が起きる(vol.229ご参照)。従って、人口問題を放置すれば、名古屋市経済が不活性化すると考えねばならず、名古屋市基本構想はこうした衰退前夜の現実を直視した上で、その趨勢を克服する処方箋の必要性を明示する必要があるだろう。
2.現在の名古屋市基本構想の立脚観 -「尾張の都」たる地位の安定に立つ姿勢-
多くの人々が知るように、名古屋市は都市誕生のルーツを1610年の清州越しに置き、名古屋城の築城と共に整備された碁盤割の城下町が近代名古屋の骨格となっている。第二次世界大戦時の大規模空襲で焼け野原となったが、復興都市計画によって城下町の骨格を残しつつ充実した道路基盤が整備され、現代名古屋の礎となっている。その後、着実な発展を遂げて、日本三大都市圏の一角を誇る大都市圏の母都市に成長した。つまり、尾張の都に始まって、日本三大都市にまで発展したという系譜である。
現基本構想では、「Ⅲ 名古屋の役割」の中で、名古屋市は「中部圏の中枢都市」として重要な役割を担っており今後もその役割を果たさねばならない、と記述されている。半世紀前の時点ではこの記述で良かったとしても、現状では異論をはさまねばならない。
2014年に地方創生が打ち出される前までは、「均衡ある発展」が国土のスローガンであったが、もはやこれはフィクションとなった。日本の総人口が減少する中で東京一極集中が是正できず、国土上では極端な優勝劣敗が顕在化する覚悟が必要な時代となったからである。従って、名古屋は中部圏を土壌に発展すれば良いという姿勢では生き残れない可能性が高い。「尾張の都」の延長的発想ではなく、国土全体を見た上で発展シナリオを構築するとともに、日本三大都市である以上、国土の発展に貢献する姿勢も示す事が名古屋の立ち位置だと解したい。
また、前述したように、名古屋市は人口のダム機能を果たしているとは言えず、さらに換言すれば中部地域の発展を牽引しているとは評し難い。「名古屋の役割とは何か」について、今日的本質論を追求しなければならないだろう。
尾張の都であり、中部圏の中枢都市である名古屋には絶対的な優位性があり、今後も安定した発展が約束されているという論調からは脱却しなければならない。
3.新しい基本構想に求めたい視点 -「国土観」と「経営的発想」-
現在の基本構想は秀逸な内容であるが、今となっては2つの視点が欠けていると筆者は思う。
第一は国土観だ。日本の国土では人口や諸機能が東京に集中する事で、家計や企業財務に高コスト負担を強いている。東京以外の立地選択が叶う事が、国民の豊かさと法人企業の国際競争力の向上に繋がるはずだ。
東京には有名大学が数多く立地し、日本最大のビジネスチャンスが存在しているから、ヒト・モノ・カネが東京に集まる事が避けられなかった事は理解できる。特に、企業本社の立地は効率性やブランド性において東京重視の価値観を持たざるを得なかっただろう。しかし、コロナ禍が産み落としたリモートスタイルは、東京にいなくてもビジネスができるという事を証明した。普段は立地コストが安くて従業員もゆとりを享受できる東京以外の都市に拠点を置き、必要に応じて東京に高速移動できる立地が、現実的な選択肢となった(企業の脱・東京現象についてvol.213ご参照)。企業経営者側に、「脱・東京」需要が生まれているのである。
リニア開業後の名古屋は、こうした立地条件を高い次元で満たすから、「脱・東京」需要を名古屋で受け止め、東京一極集中是正の受け皿となる事が三大都市としての役割だと筆者は考える。国土の高コスト構造を打破し、過密リスクを緩和する役割を名古屋が果たすという姿勢を内外に示す事で、多様な行政テーマに変革をもたらす事となるだろう。また、「中部圏の中枢都市」に留まっていては成長シナリオが描けないが、東京一極集中是正の受け皿を掲げれば成長シナリオも描ける。国土における役割と名古屋の成長シナリオは表裏一体のものであるから、これを新しい基本構想の中で位置づけて頂きたいと願う。
第二は、経営的発想である。前述したように、若者の東京流出と子育て層の近隣流出という2大問題の先には、名古屋市経済の縮退が待ち受けている。その時には、個人市民税が減少するから、名古屋市の税収が減退することとなる。ただでさえ、高齢化などによって扶助費が膨らみ、諸物価の上昇によって人件費や物件費が上昇しているから、市税収の4割を占める個人市民税が減少し始めると名古屋市の財政運営は窮状となるだろう。
また、河村前市長が実施した市民税5%減税に加えて、広沢新市長は10%減税への拡大を公約としている。総務省の指導により、地方税の減税を行う場合には、その分の行財政改革を行う事が条件とされている。つまり、減税分のコスト削減を実施しなければならないから、物価上昇局面でこれを実施するとなると、行政サービスの低下につながる懸念も生じよう。
こうした隘路を打破していくためには、税収を上げる姿勢が必要不可欠だ。名古屋市の税収は、個人市民税と固定資産税が4割ずつで、合わせて8割を占めている。前述したように、若者と子育て層の流出を放置しない事は、個人市民税の税源を確保する観点からも重要だ。加えて、若者の活躍機会となり、子育て層の所得を上げる機会ともなるよう東京から本社機能の移転を積極的に受け止めるためには、オフィスビルの供給を促さねばならない。それは都心部における再開発の推進を意味し、これを促す大胆な誘導策が必要だ(vol.187ご参照)。オフィスビルの供給が増えれば、固定資産税の増収に直結する。個人市民税と固定資産税の税源を涵養し、減税と同時に税収を能動的に上げる経営的発想が、今後の名古屋市政には強く求められ、その姿勢を基本構想の中に位置づけて頂きたい。
名古屋市が新しい基本構想の策定に踏み出すならば、国土観と経営的発想に立脚した行政指導方針が格調高く謳い上げられることを強く願っている。