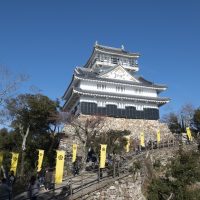名古屋市緑区鳴海町にある名古屋市鳴海工場は、平成21年(2009年)6月に完成した大規模なゴミ焼却工場だ。この鳴海工場の整備にはいくつもの特徴的な背景があった。最大のミッションは、名古屋市から出る埋め立て処分廃棄物を少なくすることだった。ゴミ焼却工場から排出される焼却灰をはじめ、破砕不燃物などは埋め立て処分されるのだが、名古屋市の埋め立て処分能力は少ない。このため、老朽化した鳴海工場の改築(建て替え)にあたっては、挑戦的な取り組みが求められたのである。
1.焼却灰の埋め立て処分量を減らせ! -ガス化溶融炉の導入-
名古屋市緑区で稼働していた旧鳴海工場は昭和45年(1970年)に稼働を開始した施設で老朽化が進んでいた。折りしものダイオキシン規制強化に対応することも困難な状況となったため、平成13年(2001年)に稼働を終えた。機械設備である焼却工場の宿命で、30年程余の稼働で限界を迎えたのである。
鳴海工場は、名古屋市南東部地域から排出される一般廃棄物を焼却する工場なのだが、新たに建て替え整備(改築)するにあたっては、大きな問題が立ちはだかっていた。名古屋市内にある6カ所の焼却工場は、全国的に一般的なストーカ式の焼却炉で、安定的な焼却が可能で維持管理がしやすい反面、大量の焼却灰が排出される特性がある。このため、焼却灰を埋め立て処分場で最終処分する負荷が大きい。ところが名古屋市は自市内の埋め立て処分能力が少なく、岐阜県多治見市にも埋め立て処分場(愛岐処分場)を確保するなどして処分に苦心している。当時、藤前干潟を埋め立て処分場にすることが検討されたが、貴重な自然資源であることに鑑み、これを諦めることとしていた(藤前干潟を守る運動は、当時社会問題に発展していた)。当然にして埋め立て処分できる量には限界があるから、愛岐処分場等に搬入する焼却灰等を少なくすることが急務だったのである。

ゴミの焼却は必要だし、最終処分量は少なくしなければならない。この2つの課題を両立させるために、ストーカ炉ではなくガス化溶融炉の導入が検討された。ガス化溶融炉は高温で燃焼するためダイオキシンが出にくく、最終的に排出されるのは溶融スラグとなり焼却灰よりも容量がぐっと小さくなる。そして溶融スラグは道路用アスファルト骨材やコンクリート骨材などとして利用することで、資源循環することが可能だ(当時はJIS規格化される直前で、資源循環の見通しを期待していた)。焼却灰を減容するためにはうってつけの方式なのである。

最終処分能力が乏しい名古屋市にとってガス化溶融炉は適性が高い方式であったが、比較的新しい技術で大都市での導入実績がなく、先端技術であるから名古屋市環境局の技師たちが培ってきたストーカ炉の知識が活かせないというジレンマがあった。しかし、事態に猶予は許されなかったため、名古屋市環境局は議論を重ねた結果、新しい鳴海工場にガス化溶融炉の導入を決めたのである。そして、この鳴海工場のガス化溶融炉には、市内南東部の家庭から排出される可燃性の一般廃棄物に加えて、名古屋市の他の焼却工場から排出される焼却灰も運び込んで混焼することにより、焼却灰の最終処分量を極力小さくする計画とされた。名古屋市環境局の英断である。鳴海工場は、名古屋市のゴミ処理を持続可能にするために、実に重要な役割を担うことになったのである。
2.PFI第一号としての整備・運営 -民間の先端技術を導入するには不可避-
ガス化溶融炉は新しい技術であるため、設計、建設に加えて維持管理・運転業務までを民間に委ねることが望ましい。これは、まさしくPFIの考え方そのものであった。しかし、当時はPFIが制度化されて間もない時期であり、名古屋市には経験がなかった。従って、名古屋市環境局は、ガス化溶融炉とPFIという二つの新しい方式の導入に当初は慎重であったと思われる。名古屋市環境局がこの問題を検討していた時期に、PFIの勉強を兼ねた基礎的な調査の依頼があり、我々が担当した際には、「多くの課題がある」という空気に支配されていたのを筆者は感じ取っていたのである。
しかし、ガス化溶融炉の導入しか道はないと判断せざるを得なくなり、そうなると必然的にPFIの導入に舵を切る必要が生じる。当時、政令市のような大規模な都市でガス化溶融炉を導入した事例はなく、PFIでこれを整備した事例もない中で、名古屋市は不退転の決意でこれを進めることを決断したと思われる。鳴海工場は規模が大きいので実験的導入などという生易しいものではないし、ガス化溶融炉という先端設備を見たことはなく、加えてPFIを未経験だった名古屋市にとって、これを進めるのは大変ハードルが高い。このため、環境局内に特別チームを組成するにあたり、「できる人材」が環境局内外から集められた。我々が呼ばれたのはその直前で、可能性調査やアドバイザー業務の内容および必要となる予算規模などについてヒアリングを受けていた。我々も事の重大さを察知し、相応の体制を敷いて臨む決意をしたのである。
平成13年(2001年)4月に名古屋市環境局とMURCの双方にチームが出来上がり、検討が始まったが、それは未開の地を拓く開拓団のような道のりであった。最初は、打合せ資料の完成度を求める名古屋市と、暗中模索で進めるしかないと考えるMURCでかみ合わなかった。しかし、一つ一つの課題を丹念にクリアする姿勢を堅持した我々は信頼を得るに至り、最終的にはガス化溶融炉を前提にサービス購入・BTO方式を国内で初めて採用し、募集する結論へとたどり着いた。当時の名古屋市環境局の主幹、主査、担当者は、使命感に燃えて仕事にあたっており、我々と熱い議論を重ねるとともに、庁内調整に奔走していた。我々にもその熱量が伝搬し、日夜没頭したのである。
3.事業者公募の舞台裏 -業界内外から関心を集めた事業者選定-
ガス化溶融炉には、シャフト炉式、流動床式、キルン式、ガス改質式などの方式があり、各メーカーがしのぎを削っていた。名古屋市がガス化溶融炉の導入を検討していることが伝わると、各社は営業活動を活発化させた。新しい技術の納入実績は各社とも欲しいし、名古屋市という大都市での大型施設の実績となればなおさらである。また、資金調達規模も大きかったため、金融機関の関心も集めた。
しかし、日量530トンという大規模な量を安定焼却する技術力、他所灰を受け入れて溶融する能力、発熱量を活用して売電事業を行うエネルギー効率性など、鳴海工場に求められる条件に照らしていくつかの方式は自ずと外れていくこととなった。最終的に応募したのは新日鉄グループと神戸製鋼所グループの2グループであった。
ところが提案書の締切当日(平成16年8月)にトラブルが待っていた。応募申請していた2グループのうち、1グループの提案書が締切時刻直前になっても届かないのである。そこに応募者からの電話が入った。市役所の駐車場には到着しているものの、提案図書が分厚く、提出部数も多いため搬入に手間取ってスタックしているという。おそらく、ギリギリまで提案書を作り込み、印刷・製本に時間を要し、飛び込んで来たまでは良いが、思いのほか運搬に難儀したということだろう。応募者は汗だくで必死の形相だったという。多くの関係者が大量の時間を投入して作り上げた提案書だから無理からぬ話だ。簡単には引き下がれまい。市役所敷地内に到着していたということで、応募書類は無事受理され、2グループによる審査競技が行われることになった。名古屋市環境局の粋な計らいであった。
技術的には双方ともに評価される点が多々あったが、新日鉄グループの提案は技術的な利点と手厚い対応姿勢が濃密に記載されていたほか、全項目にわたって充実した内容が緻密に記載されていた。分厚い組織力にモノを言わせた迫力がひしひしと伝わる提案書であった。しかし、課題がなかったわけではない。その代表がコークスだ。新日鉄が溶鉱炉で培ってきたシャフト炉式ガス化溶融炉は、多くのコークス使用を必要とした。これが脱炭素化に逆行しないかという懸念と、コークスの市場価格の変動による支払い費用の流動性の問題などである。しかし、こうした課題はあるものの、可燃ごみと他所灰を高温燃焼して溶融する能力が高く、売電量が大きいことなどから、メリットが課題を上回ると審査委員会では判断された。
こうして鳴海工場のPFI事業契約が平成17年3月に締結され、新日鉄グループによる設計、建設、資金調達が行われた。工事は順調に進み、平成21年6月に稼働を開始して現在も稼働を続けている。鳴海工場が果たした役割は大きい。名古屋市のゴミ焼却灰を自市内で減容する仕組みを構築したのであり、その後は鳴海工場の例に習い令和2年に北名古屋工場でもPFI事業でシャフト炉式ガス化溶融炉を新規に稼働させるに至っている。これによって名古屋市の焼却灰の減容能力はさらに高まった。
また、名古屋市におけるPFI事業第一号となってその後のPFI事業への道を拓いた点も大きな成果である。PFIに代表される「民活」は、「民間事業者の能力を活用する」ことを指すが、その能力とは①技術的ノウハウ、②経営ノウハウ、③資金調達ノウハウである。鳴海工場は、この3つの全てについて民間事業者の能力を求めたのであり、名古屋市にとって最初のPFI事業でありながら、真骨頂ともいえる事業となったのである。