2024年度に実施されている「なごや水道・下水道連続シンポジウム(計3回)」の第1回開催の模様が「まるはっちゅーぶ」で公開されている。能登半島地震の教訓を基に名古屋市の上下水道の地震対策について、第一線で活躍する2人の技術者の話と名古屋大学減災連携研究センターの平山准教授の示唆は大変興味深い。公開されている動画の中から、いくつかの場面を紹介して名古屋市の上下水道文化の醸成に繋げたい。
1.名古屋市公式YouTube「まるはっちゅーぶ」 -シンポジウムの模様を丸ごと公開-
「まるはっちゅーぶ」の生活チャンネルで上下水道局連続シンポジウム(第1回)の模様が公開されている(なごや水道・下水道連続シンポジウム ー第1回”地震に強い”水道・下水道を考えようー (youtube.com))。平山准教授の基調講演を0:00~40:32、名古屋市水道担当の高倉課長の講演を40:56~56:18、下水道担当の太田課長の講演を56:20~1:09:07、筆者も登壇したパネルディスカッションを1:09:32~1:54:23で視聴する事ができる。
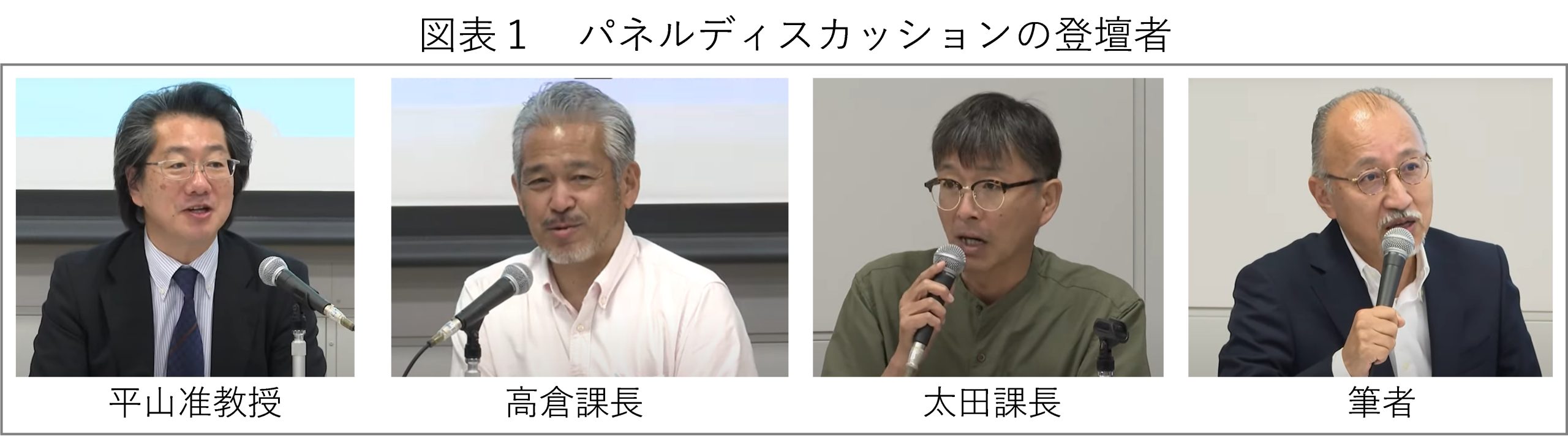
平山准教授は衛生工学が専門で、上下水道システム、災害レジリエントを研究している第一人者だ。高倉課長と太田課長は、能登半島地震で現地支援に赴き、現在も支援活動を行っている名古屋市上下水道局の技術者のリーダー格だ。これらの専門家が登壇したパネルディスカッションでは、名古屋市の上下水道の耐震化に係る現場の努力と苦悩を伺い知ることができる。パネルディスカッションの中から、筆者が記憶にとどめたいと感じた部分を抜き出して紹介してみたい。
2.危うさを「言い難い」風土 -伝える側と聞く側に努力が必要-
まず、地震に備えた耐震化の取り組みについて、現場を担当する上下水道の二人の技術課長に「今の実態をどう評価するか」と聞いた。すると、水道担当の高倉課長は、市内の水道管の総延長約8,400キロのうち1年間で実施できる工事量が100kmなので、全てを耐震管に置き換えるには80年かかると発言した。名古屋市の耐震管の設置割合は36.9%だ。また、下水担当の太田課長は、下水管のうち重要管路に限れば更新改築を92%済ませているが、総延長約7,900kmに対して改築できるのは1年間で45km/年(内、重要管路は10km/年)なので、まだまだかかると発言した。
二人の技術者は「最大限の努力をしているが、名古屋市の管路の全てに耐震化を施すのは困難だ」と滲ませたのである。困難な状況を説明してはいるが、「地震が来るまでに間に合わない」とは言えず、「危険な状況だ」とも明言しない。安心を届けたいという思いが「危うい」と決定的に表現する事にブレーキをかけている。
これを聞いた平山教授は、名古屋市は東海地域では間違いなく耐震化が進んでいるとした上で、「危うさを言い難い風土」が日本にはあり、これを市民社会で共有できないことが危険だと指摘した。市民とマスコミが意識を持って上下水道の「危うさを共有」する姿勢を持つことが重要と気づく。南海トラフ地震のような巨大災害が起きた時、名古屋市の上下水道も甚大な被害を受けるのは確実で、これへの備えを当局の耐震化工事だけに任せていては乗り越えられない。伝える側も聞く側も一層に努力をして、市民社会として心構えを持つ事が重要という事だ。

3.ヒト、データ、カネは大丈夫か? -データは大丈夫、ヒトは足りない、カネは…-
次に、耐震化を進めるためにヒト、データ、カネの何が不足しているかを二人の名古屋市の技術者に聞いた。これに対して二人ともデータは備えていると答え、ヒトは十分とは言えないと口を揃え、カネについては心配の思いを共に滲ませた。ここでもカネについては「言い難い」模様である。
そこで、カネのやりくりについて、司会を担当していた経営企画課の安達課長に発言を振った。すると、R4年度に収支が「赤字に転落」したとあっさりと認めた。上下水道局は公営企業であるから、市民が負担している料金収入で経営しなければならない。そして、利益が出ればこれを耐震化対策に使うという構造だから、赤字になったという事は耐震化に予算を割く源資が枯渇に向かっているという事を意味する。
仮に、現状の耐震化予算を維持できたとしても、人件費や資材の高騰や労働者不足の現状からすると耐震化の工事進捗は遅くなると二人の技術者は認め、今後は老朽管路の更新期を相次いで迎えるため、耐震化すべき工事対象は増えると見込んでいた。
また、平山准教授の基調講演で、名古屋市では管路の総延長を上下水道局の技術者数で除すると1人当たり16.7kmを担当せねばならないと指摘したが、この数値は技術者が到底足りないという事を示唆するものだ。
つまり、名古屋市の上下水道管の耐震化対策には、データはあってもヒトとカネが不足して工事が停滞する懸念が潜んでいることが明らかとなったのである。
4.名古屋の水文化の醸成とは -水を守る水文化を市民が培うために-
パネルディスカッションの終わりに、参加した市民から質問を受けた。すると市民からは「水道工事は何度も掘り返して工事期間が長いが、工事中に断水しても良いので掘るのを一度で済むように工事をすれば早くなるのでは?断水に備えるためのドラム缶を配ってもらいたい」という発言が出た。この質問者は、市民が不便を許容するから工事を迅速に進めることを提案したものだ。
これに対し、高倉課長は断水を起こさないように工事をすることの重要性を説いた。水道を利用しているのは一般市民だけではなく、経済活動全般で利用しているため、断水の許容を求める事は単純な話ではないという背景があるものと思われる。一方、平山准教授からは、米国では最初に掘ったら工事が終わるまで鉄板を被せて工事を行い、最後に埋め戻す工法を採用していると紹介した上で、日本では道路管理者がこれを許可していないと縦割り行政の実情を紹介した。
市民が不便を許容すべき事について、市民から発言があったのは水文化の醸成に向けて明るい兆しだ。但し、水文化の中心を不便の許容に置くのではなく、地震が起きた時の応急活動における市民の役割に重点が置かれることが望ましい。我々の水を守る知識を底上げして、地震発災後のような非常時には市に頼りきりにならずとも必要最低限の水を確保できる知識と意識を持つ事が、名古屋市の水文化醸成の求められる在り方だろう。例えば、家庭で水の備蓄はできているか、各小学校に設置されている応急給水栓の存在を知っているか、またその使い方を知っているか。非常時に市民自らの力で必要な水を守る知識と意識を培うために日頃から関心を持ち、地域で互いに啓発し合う市民社会を構築していくことが必要なのだ。
耐震化対策は、まだまだ道のりが長く、コスト増加や人手不足がこれに立ちはだかっている。我々が無知のまま物理的な耐震化対策にのみ依存していては、名古屋市はレジリエントな都市にはなれない。斯く言う筆者も含め、名古屋市の上下水道についてより多くの知識を学び、日常的に意識を高め合う市民になりたいものだ。なごや水道・下水道連続シンポジウムが、その一助になることを切に願ってやまない。




















